










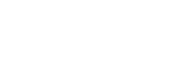











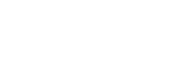
家庭科 4択問題
卵料理でいちばんシンプルなのは、なんと言っても「卵かけご飯」。日本で初めて「卵かけご飯」を食べたのは、一体いつ頃の人だとされているでしょう?
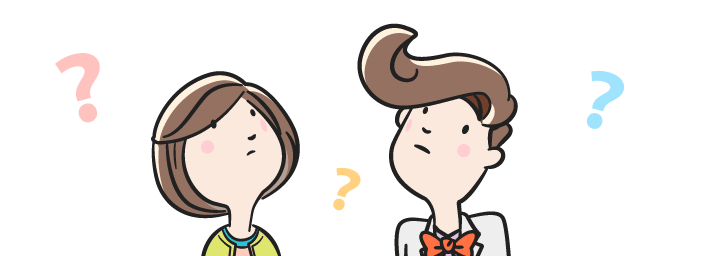
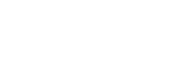
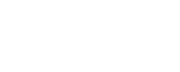
「卵かけご飯」が記録に登場するのは明治時代の新聞記者・岸田吟香の手記です。1927(昭和2)年発行の雑誌「彗星江戸生活研究」には、吟香が朝食に食べていた「元祖卵かけご飯」は、ご飯に生卵、塩、唐辛子をかけたもので「鶏卵和(けいらんあえ)」と呼ばれていたそう。なお長らく肉食が禁じられていた日本では、卵料理が一般化したのが江戸時代からで、炊き立てご飯に卵を乗せて蒸し焼きにした「玉子飯」など、かなり卵かけご飯に近い料理も食べられていたようです。

「卵かけご飯」が記録に登場するのは明治時代の新聞記者・岸田吟香の手記です。1927(昭和2)年発行の雑誌「彗星江戸生活研究」には、吟香が朝食に食べていた「元祖卵かけご飯」は、ご飯に生卵、塩、唐辛子をかけたもので「鶏卵和(けいらんあえ)」と呼ばれていたそう。なお長らく肉食が禁じられていた日本では、卵料理が一般化したのが江戸時代からで、炊き立てご飯に卵を乗せて蒸し焼きにした「玉子飯」など、かなり卵かけご飯に近い料理も食べられていたようです。